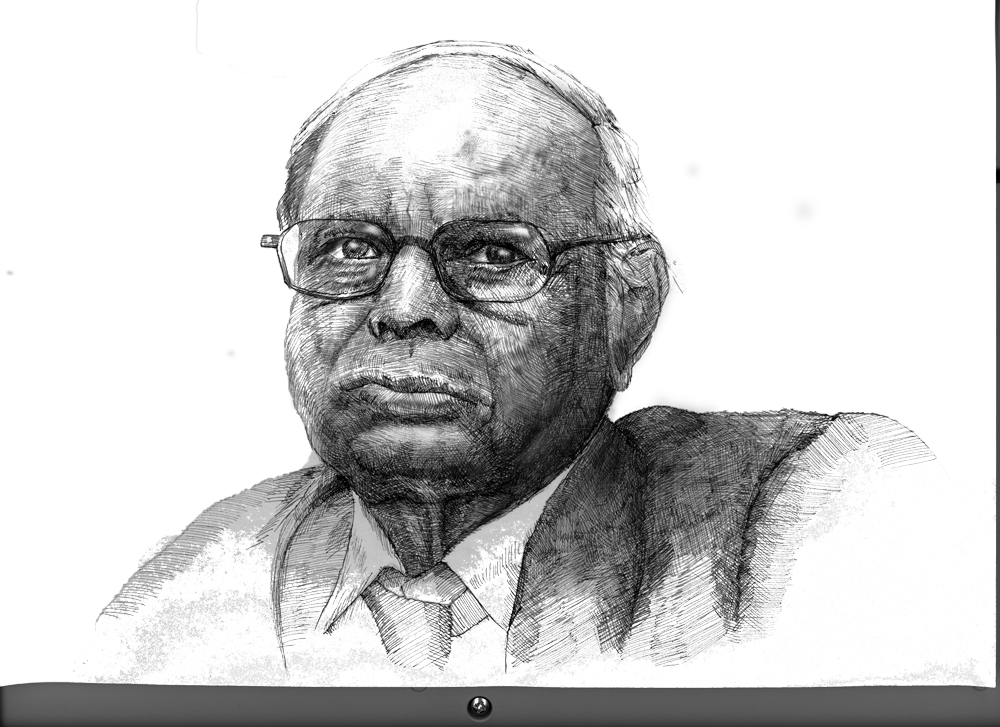はじめに
1991年に開始されたインドの経済自由化(構造調整プログラム)の重要な柱の政策として金融制度の改革があった。銀行部門や証券部門での大規模な規制緩和が行なわれ、独立後に形成されてきた様々なインド独自の金融制度が大きく変革された。こうした金融制度改革の結果、その他の規制緩和の効果も加わり、21世紀のインドはIT産業を中心に世界経済でも経済自由化以前とは比較にならない大きな役割を担うようになった。
内容をご覧になるには・・・ ログインが必要になります。ログインには、シリアル番号が必要になります。 シリアル番号は、下の注文ボタン「シリアル番号を購入」からご購入いただくと、メールにてお送りします。 購入後に送られてくるメールに書かれたシリアル番号を「新規ユーザー登録」フォームに、他の情報とともに入力いただくと、閲覧できるようになります。 (「通常の紙の本を購入」の場合、発送されてきた本を入手後、巻末に記載されたシリアル番号を、「新規ユーザー登録」に他の情報とともにご入力ください)