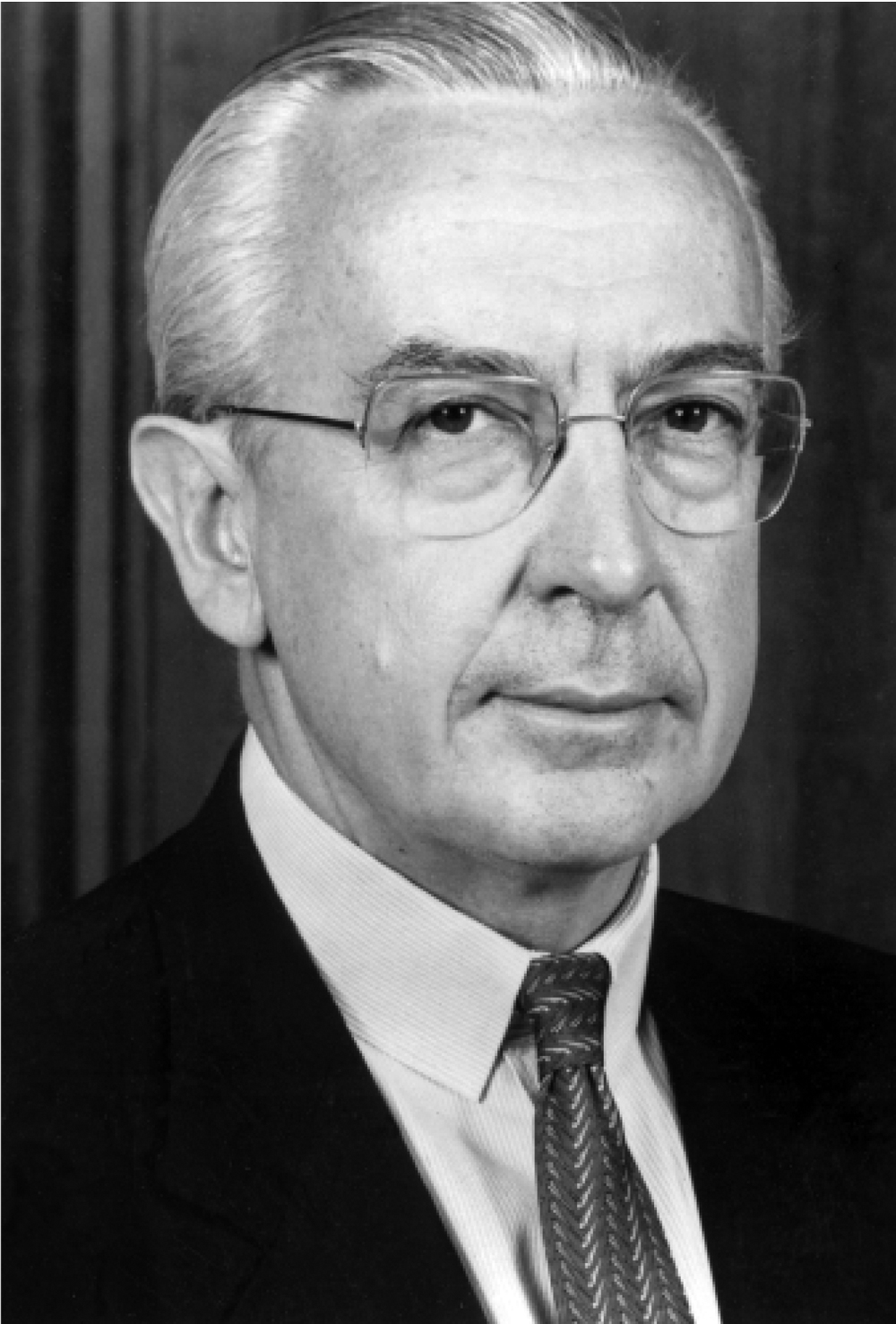フランス人の苗字で「ド」(de, du または音便のd’など)が付くのは貴族の出自をもつ、という(やや不正確な)言い伝えがある。日本語でいえば「藤原道長」を「藤原の道長」と呼ぶときの「の」に近い語感だろうか。いわれてみればドゴール(Charles de Gaulle)やジスカール・デスタン(Valéry Giscard d’Estaing)など、歴代大統領のなかでも、その正統性の真偽はともかく「貴族的」な人物は苗字に「ド」が付いている。
[cap……このエントリーを表示する権限がありません。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。