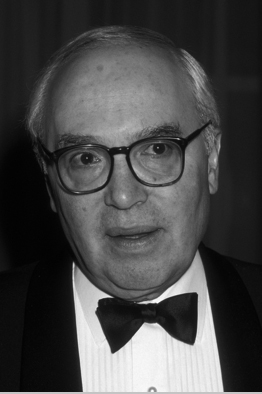はじめに
米国の独立戦争による建国以来の経済発展を想起したとき、最初に気付くのは、連邦主義(上からの中央集権的な国民経済的発展)と反連邦主義(下からの草の根的地域的な経済発展)との根強い反目と対立である。これは、1787年に制定された合衆国憲法が人民主権を基礎とした共和制を基本とし各州に大幅な自治を認める一方で、同時に中央政府の権限を強化する連邦主義を採用したことの相剋から由来するものであった。したがって、共和党︱民主党という二大政党の政治上の……
このエントリーを表示する権限がありません。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。