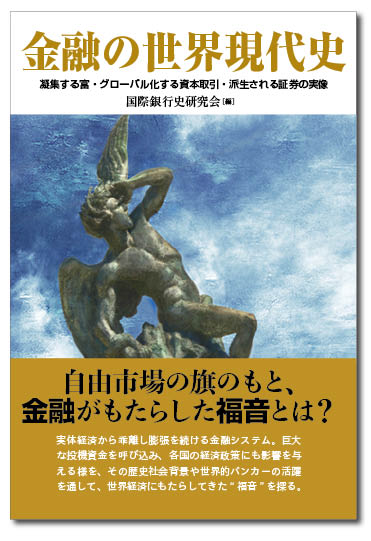私たち国際銀行史研究会は2012年に『金融の世界史』と題する本を悠書館から刊行させていただいた。同書は内容の硬い歴史書ながら、幅広い読書人に迎えられ、学会誌『社会経済史学』はもとより、『日本経済新聞』『エコノミスト』等の経済メディアに取り上げていただき、BSフジ「原宿ブックカフェ」(2013年3月15日)でも放映され、さまざまなご教示をたまわることができた。ご教示はおおむね好意的だったが「歴史と現代とのつながりがみえにくい」というご指摘もいただいた。たしかに前書は……
このエントリーを表示する権限がありません。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。